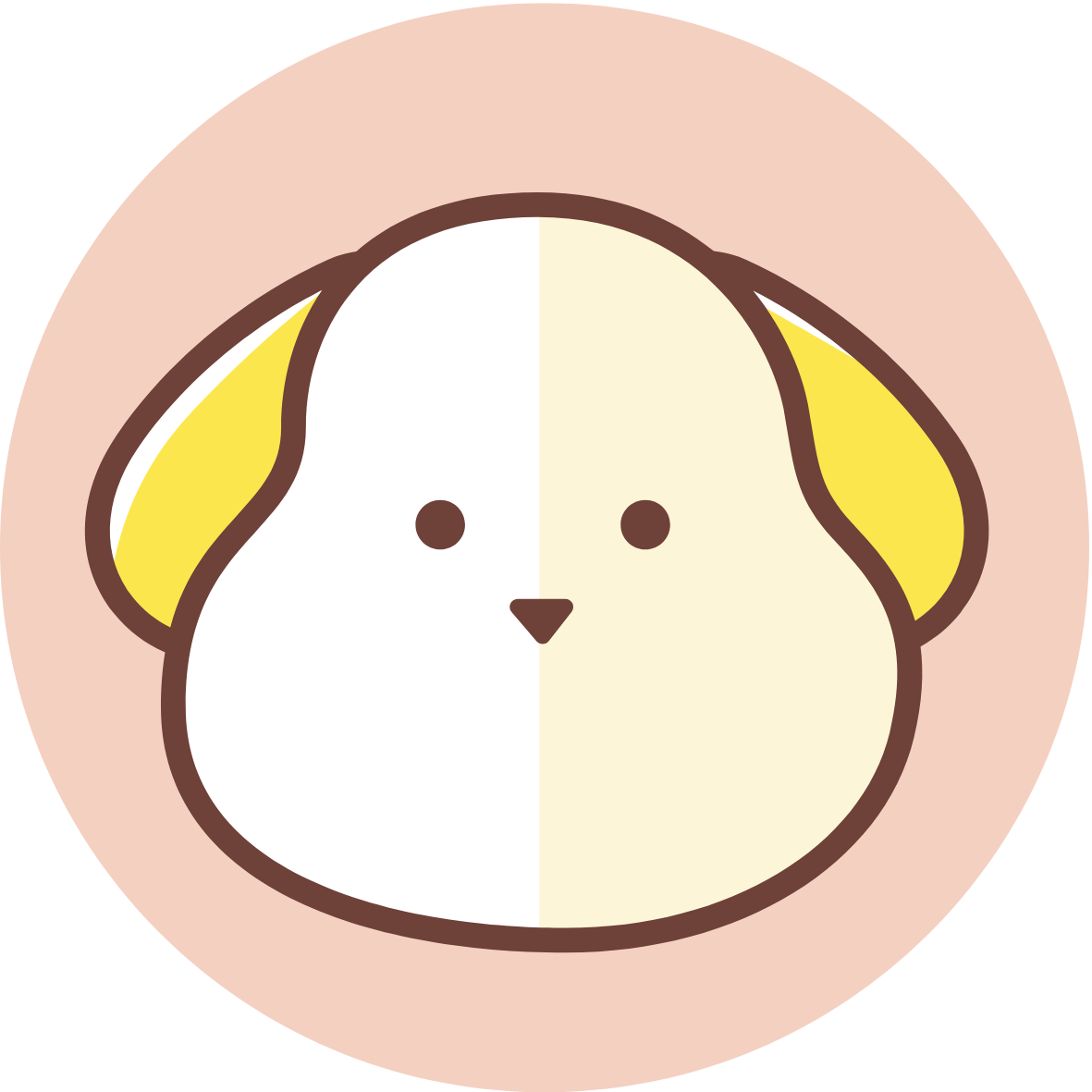墳墓記(髙村 薫・新潮社)言葉の霧の中を歩いた本 ― 番外編

今回は番外編です。読んだけど繊細さん向け?ではないと思いつつ…
せっかく頑張って読み切ったのでご紹介します。
あらすじ
「墳墓記」は、自死を試みて病院に運ばれた主人公が、管につながれたまま夢と現実の境を漂う場面から始まります。そこから物語は不思議な展開を見せます。
現代の言葉や古語、和歌、漢語、歴史、能楽などが音のように入り乱れ、主人公の人生の断片が浮かび上がっては消えていきます。
物語は大きな起伏を描くことなく、淡々とした感覚の連続として進みますが、その背後には常に「死」の影が漂っています。祖父、父、娘――身近な死者たちの記憶が、主人公の意識を包み込んでいきます。
起伏が少ないところは繊細さん向けかも…
感想
読み進めるうちに、何度も「わからない」と感じて立ち止まりそうになりました。
言葉が複雑に交錯し、意味をつかむのが難しいからです。それでも、主人公の夢のような語りを聴いていると、死というものがずっと背後にあることだけは強く伝わってきました。
祖父や父、娘の存在が、静かにしかし確実に死の気配を呼び込んでいて、読んでいる自分の背筋がゾッとする瞬間もありました。
そして、はっきりした答えは見えないものの、主人公は人生を振り返る中で「常に死を背後に感じたまま生きる感覚」を得ているようにも感じました。
大きなドラマはなく、淡々とした語り口や言葉の響きが続くので、繊細な人にとっては安心して読めるかもしれません。
まとめ
「墳墓記」は、筋を追う物語というよりも、死に瀕した人間の意識を描いた作品でした。
わかりにくさを抱えたままでも、そこに「死が背後にある」という感覚を受け取ることができる。それを感じ取るので精一杯でした。
ただ、主人公が感じていた「常に死を背後に感じたまま生きる感覚」を自分もちょっとだけ共有できた気がします。
文章を「音として楽しむ」と心穏やかに読めました。
またチャレンジしたい作品です。